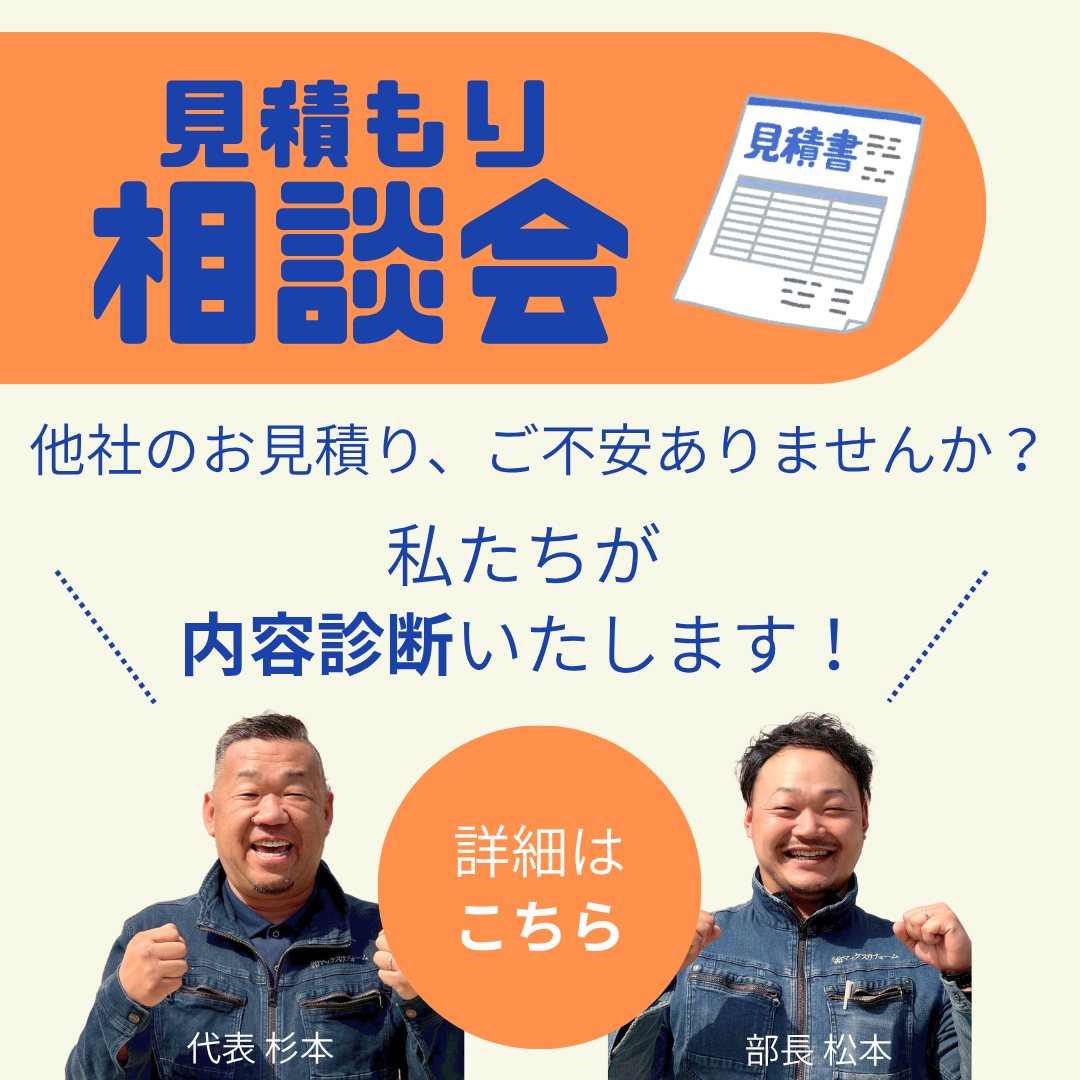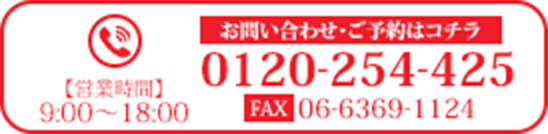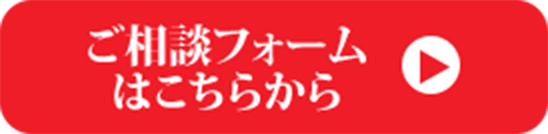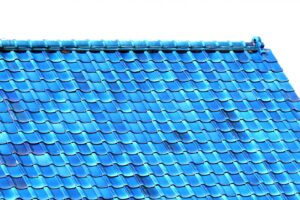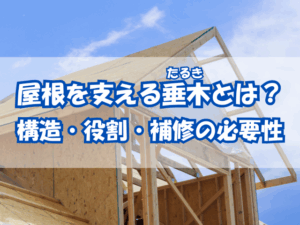軒裏修理の費用相場は?劣化原因と修理方法を徹底解説

住まいの中でも、意外と見落とされがちな「軒裏(のきうら)」。
しかし軒裏の劣化を放置していると、雨漏りや外壁の傷み、さらには建物全体の寿命にまで悪影響を与えてしまうことも…。
そこで今回は、軒裏修理の費用相場、劣化原因、修理方法を中心に、わかりやすく徹底解説していきます!
軒裏修理が必要な理由とは?
軒裏とは、屋根の下端が外壁より外に張り出している部分の裏側を指します。ここには、以下のような重要な役割があります。
- 雨水や風から外壁を守る
- 夏場の強い日差しを遮る
- 屋根裏の換気を促す
- 美観を保つ
軒裏が劣化すると、単に見た目が悪くなるだけでなく、建物内部への水の侵入や、カビ・腐食の原因にもなります。そのため、早めの点検と修理が必要なのです。
軒裏が劣化する主な原因
雨水の侵入
軒裏が劣化する最も一般的な原因は雨水の侵入です。屋根材や雨樋が傷んでいると、雨が直接軒裏に伝わり、木材や下地に水分がしみ込みます。これを放置すると、軒裏材が腐食し、剥がれや穴あきが発生するリスクが高まります。特に台風やゲリラ豪雨など、集中豪雨の多い地域では注意が必要です。
湿気と結露
軒裏は屋根裏とつながっているため、通気が不十分だと湿気が溜まりやすくなります。外気との温度差で結露が発生し、軒裏材に水滴が付着。これがカビや腐朽菌の繁殖を招き、じわじわと木材を弱らせていきます。換気口の設置や定期的な点検で、湿気対策を講じることが重要です。
紫外線と風化
常に屋外にさらされる軒裏は、紫外線によるダメージも受けています。塗装の劣化や表面材の乾燥・ひび割れは、紫外線による酸化が進むことで起こります。特に南向きの軒裏はダメージが蓄積しやすいため、塗装メンテナンスの頻度を高めることが効果的です。
シロアリ・害虫被害
軒裏に使われている木材部分にシロアリが侵入すると、短期間で内部から食害が進行します。また、軒裏は蜂などが巣を作りやすい場所でもあり、放置すると建材の破損や二次被害につながることも。定期点検と、異変を感じたら早期対応が求められます。
地震や台風などの自然災害
日本は自然災害が多い国です。地震で建物が揺れると、構造的に弱い軒裏部分にひび割れが生じたり、接合部が緩んだりします。また、台風による強風で軒天材が吹き飛ばされたり、雨樋ごと破損するケースもあります。災害後には必ず軒裏の状態をチェックし、早めの修繕を行いましょう。
経年劣化
どんなに丁寧に施工された軒裏でも、20〜30年経過すると自然に劣化が進みます。材料の乾燥や収縮、ビスの緩み、塗膜の剥がれなどが少しずつ積み重なり、見た目や性能に問題が出てきます。築年数に応じた定期点検と、劣化症状に合わせたメンテナンスが重要です。
軒裏修理の費用相場はどれくらい?

軒裏修理の費用は、修理方法・範囲・使用する材料によって大きく変わります。一般的な費用感は以下の通りです。
軒裏修理の費用相場表
| 工事内容 | 費用目安(1m²あたり) | 特徴 |
| 軒裏の部分補修 | 8,000〜15,000円 | 小規模な破損に対応 |
| 軒裏の全面張り替え | 15,000〜25,000円 | 広範囲の劣化・リフォームに最適 |
| 軒裏塗装 | 3,000〜6,000円 | 表面の防水性・美観回復 |
| 軒裏換気口の交換 | 5,000〜12,000円 | 換気性能の改善 |
| シロアリ対策・防虫施工 | 10,000〜20,000円 | 害虫被害の予防・修復 |
修理にかかる総額の目安
- 小規模な軒裏修理(部分補修+塗装):5万円〜10万円前後
- 中規模な軒裏修理(部分張り替え+塗装):10万円〜30万円前後
- 大規模な軒裏修理(全面張り替え+塗装+換気口交換):30万円〜60万円以上
※高所作業や足場設置が必要な場合、別途10万円〜20万円の費用が加算されることもあります。
軒裏修理の具体的な方法
1. 軒裏材の部分補修
軒裏材の一部のみが破損している場合、劣化箇所だけを撤去し、新しい部材に差し替えます。
剥がれやひび割れ、小さな穴など局所的な損傷に適しています。
周囲の軒裏と色や素材を合わせることで、見た目も自然に仕上げられます。部分補修は費用が抑えられるため、早期発見・早期対応がコスト削減にもつながります。
2. 軒裏材の全面張り替え
広範囲に劣化が進行している場合は、部分補修では対応できないため、既存の軒裏材をすべて撤去して新たに張り替えます。下地に問題があれば、同時に補修・補強を行うことも重要です。全面張り替えは工期が長くなりやすいですが、美観と耐久性を一気に回復できるメリットがあります。
3. 軒裏塗装
補修や張り替え後に必ず行いたいのが塗装作業です。
軒裏材を保護し、防水性・防カビ性を高めるためには、耐候性塗料や防カビ塗料を使用するのが効果的です。
また、既存の軒裏の色あせや汚れが目立つ場合も、塗装だけでリフレッシュできることがあります。施工後5〜10年を目安に再塗装を検討するとよいでしょう。
4. 換気口の交換・新設
湿気対策の一環として、軒裏に換気口を設置・交換する工事も重要です。
従来よりも高性能な換気口に交換することで、屋根裏や軒裏内部の結露リスクを大幅に減らすことが可能です。
特に築年数の古い住宅では、換気機能が十分でないケースが多いため、軒裏修理と併せて検討するとよいでしょう。
5. 防虫・防腐処理
木材部分の軒裏では、防虫・防腐対策が欠かせません。
シロアリ駆除剤や防腐剤を散布・塗布して、被害の再発を防ぎます。軒裏張り替え時や補修時に合わせて行うことで、長期的な耐久性向上に貢献します。
また、防虫ネットの設置による小動物・害虫の侵入対策も有効です。
軒裏修理に使われる主な材料

ケイカル板(軽カルシウム板)
- 耐火性・耐水性に優れており、現在の軒裏工事で主流。
合板(ベニヤ板)
- コスト重視の場合に選ばれるが、耐久性はやや低め。
スタイロフォーム(断熱材)
- 断熱性能を重視する場合に使用されることも。
軒裏修理を依頼する業者選びのポイント

1. 軒裏修理の実績が豊富な業者を選ぶ
軒裏修理は、屋根工事や外装リフォームとは異なる専門性が求められます。
過去の施工事例が豊富で、軒裏材の種類や症状に応じた柔軟な対応ができる業者を選びましょう。
特に、部分補修と全面張り替えの両方に実績がある業者は、建物の状況に最適な提案をしてくれる可能性が高いです。
2. 施工内容と見積もりを丁寧に説明してくれるか
信頼できる業者は、現地調査の段階から問題箇所をわかりやすく説明し、工事内容・工期・見積もり金額についても詳細に伝えてくれます。
“一式〇〇万円”といった曖昧な見積もりではなく、材料費・施工費・足場費用など、内訳が明確な見積書を提示する業者を選ぶことが大切です。
わからない点を質問した際、丁寧に回答してくれるかもチェックポイントです。
3. 保証制度の有無を確認する
軒裏修理後のトラブルに備えるため、施工保証がある業者を選びましょう。
特に、施工不良による再修理や雨漏り発生に対応してくれる保証が付いていると安心です。保証期間や保証内容について、事前に書面で確認しておくことも忘れずに行いましょう。
軒裏修理のタイミングを見極めるポイント

軒裏の異変チェックリスト
- 板が剥がれている
- 軒裏に黒ずみやカビがある
- 軒裏に穴やひび割れが見える
- 軒裏材が膨らんでいる、波打っている
- 雨漏りの形跡がある
これらのサインが見られたら、早めに専門業者へ相談することをおすすめします。
軒裏修理に火災保険が使えるケースも!

軒裏の破損が自然災害によるものであれば、火災保険を利用して修理費用を補償してもらえる場合があります。特に対象となりやすいのは、以下のケースです。
火災保険が適用される主なケース
- 台風・強風による軒裏材の剥がれ、破損
- 落下物(樹木や看板など)による損傷
- 大雪による荷重で軒裏が崩れた場合
- 地震保険に加入している場合の地震による破損(※通常の火災保険ではカバーされない)
火災保険を適用する際のポイント
- 被害発生から速やかに保険会社へ連絡すること
- 被害発生から時間が経つと、保険適用が認められにくくなります。
- 損傷箇所の写真を必ず撮影しておくこと
- 施工前・施工後の記録写真が重要な証拠になります。
- 専門業者に見積書・被害報告書を作成してもらうこと
- 保険会社へ提出するため、第三者による客観的な書類が必要です。
- 免責金額や補償限度額を事前に確認しておくこと
- 契約内容によっては一部自己負担が発生することもあります。
注意点
- 経年劣化や施工不良による破損は保険対象外となることが多いです。
- 故意や重大な過失による破損も補償対象外です。
火災保険をうまく活用することで、軒裏修理の自己負担を大きく減らすことができます。被害が発生したら、まずは保険証券を確認し、信頼できる業者と連携して申請を進めることが大切です。
火災保険が適用される主なケース
- 台風・強風による軒裏材の剥がれ、破損
- 落下物(樹木や看板など)による損傷
- 大雪による荷重で軒裏が崩れた場合
- 地震保険に加入している場合の地震による破損(※通常の火災保険ではカバーされない)
火災保険を適用する際のポイント
- 被害発生から速やかに保険会社へ連絡すること
- 被害発生から時間が経つと、保険適用が認められにくくなります。
- 損傷箇所の写真を必ず撮影しておくこと
- 施工前・施工後の記録写真が重要な証拠になります。
- 専門業者に見積書・被害報告書を作成してもらうこと
- 保険会社へ提出するため、第三者による客観的な書類が必要です。
- 免責金額や補償限度額を事前に確認しておくこと
- 契約内容によっては一部自己負担が発生することもあります。
注意点
- 経年劣化や施工不良による破損は保険対象外となることが多いです。
- 故意や重大な過失による破損も補償対象外です。
火災保険をうまく活用することで、軒裏修理の自己負担を大きく減らすことができます。被害が発生したら、まずは保険証券を確認し、信頼できる業者と連携して申請を進めることが大切です。
軒裏修理に関するよくある質問
Q1. 軒裏修理はどの季節に行うのがベストですか?
一般的には、雨の少ない春や秋がおすすめです。梅雨や台風シーズンを避けることで、工事の延期リスクが少なく、スムーズに作業が進められます。ただし、被害が進行している場合は季節を問わず、早めに対応することが最優先です。
Q2. 軒裏の塗装と張り替えで迷ったらどうすればいい?
まずは劣化の程度をしっかり見極めることが大切です。表面の塗膜が劣化しているだけなら塗装で十分ですが、板材自体が膨らんでいたり、剥がれ・腐食が進んでいる場合は張り替えを検討しましょう。
目に見える範囲だけで判断せず、できれば専門業者に現地調査を依頼し、内部の状態までチェックしてもらうと安心です。
無理に塗装だけで済ませると、後から再工事が必要になるケースもあるので、将来のメンテナンス費用まで考えて選ぶのがおすすめですよ。
Q3. DIYで軒裏修理はできる?
小さな塗装補修程度ならDIYも可能ですが、基本的にはおすすめしません。高所作業になるため危険が伴いますし、適切な下地処理や材料選び、施工技術が求められるため、プロに依頼した方が結果的にコストパフォーマンスが良くなります。
Q4. 軒裏修理と一緒に行うと良い工事は?
雨樋の交換や屋根の点検・補修を同時に行うと、足場代を節約できて効率的です。また、外壁塗装や換気設備の見直しも軒裏修理と相性が良く、家全体の耐久性向上につながります。
まとめ:軒裏修理は早めの対策がカギ!
軒裏は、建物を雨・風・日差しから守る重要な役割を担っています。小さな劣化だからと放置してしまうと、将来的に大規模な修繕が必要になり、費用も膨らんでしまいます。
この記事でご紹介した劣化原因・修理方法・費用相場を参考に、定期的な点検と早めの修理を心がけましょう。
軒裏を適切にメンテナンスすることで、住まい全体の耐久性と快適性をぐっと高めることができます!
早期発見・早期対応で、大切なマイホームをしっかり守っていきましょう!
ご相談・無料点検はこちら

屋根の不具合は、早めに気づいて対処することが何より大切です。
「見てもらうだけでもいい?」 「とりあえず相談だけ…」 という方も大歓迎!
匿名相談やLINEからの気軽なご連絡も受け付けています✨
電話番号: 0120-254-425
メールアドレス: info@maxreform.co.jp
お問い合わせフォーム: こちらをクリック
公式LINE: LINEでお問い合わせ
予約カレンダー: こちらをクリック
信頼のサービスで、皆様の高槻での暮らしをしっかりとサポートいたします✨